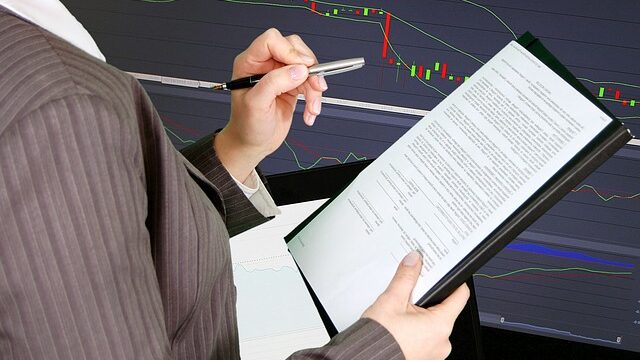先日、2023年の投資方針をまとめる中、急遽思いつき、反応してしまったマネックス証券へのiDeCo口座移管。

そして考えたら行動してみたくなる性格なところもあり、実際に移管を開始。

手続きが少し進み、返送が必要な書類が届きました。
(申請からおおむね10日前後で手元に届くはず)
記載する内容は簡単、時間も無駄にしたくないので、さっさと返送。
今日は返送までに必要な内容などを簡単にまとめておきます。
届いた資料一式
加入申し込みのため、届いた封筒に同封されていた資料は、以下のようなものでした。
| 資料の概要 | 補足 |
|---|---|
| ①送付状 | 挨拶文とiDeCo専用ダイヤルの連絡先など記載あり |
| ②iDeCo簡単ガイドブック | 制度の概要や商品紹介、運用の考え方などを記載したマネックス証券のiDeCo総合パンフレット |
| ③確定拠出年金 配分指定書(個人型掛金用)【要返送】 | 拠出金の配分指定⇒記載・確認内容(概要)は下に記載 |
| ④加入者等運営管理機関変更届【要返送】 | 運営管理機関の変更、移管時の配分指定⇒記載・確認内容(概要)は下に記載 |
| ⑤記入や訂正方法の記載例 | 書類④の記入例 |
| ⑥申込に対しての留意事項など | 記入上の注意点などを記載した書類 |
| ⑦加入、移換にあたっての確認事項 | iDeCo制度の特徴や拠出限度額など、制度に関する概要知識を記載した書類 |
| ⑧返信用封筒 | 書類③、④を返送するための封筒 |
以下のような方であれば、重要なのは「書類③、④」を記載し、返信用封筒で返送するだけです。
小難しくはありませんので、簡単に手続きは完了できます。
- すでにiDeCoの制度を把握している方
- マネックス証券の商品ラインナップを把握している方
- 投資のリスクや運用を経験している方
ガイドブックなどを読み知識を深めながら、という方は読む分の時間はかかるでしょうが、一読しておくのもアリかと思います。
概要はこの程度として、以下は提出が必要な書類③、④について、記載する内容などの概要を紹介しておきます。
確定拠出年金 配分指定書(個人型掛金用) (資料③とした書類)
こちらの資料は「拠出金を移管先で各商品へどのように配分するか指定する」ために必要な書類です。
指定するといってもオンラインで申請されている方はすでに設定が反映されているはずですから、配分は確認する程度でしょう。
わたしは以下の部分に注意して確認・記載しました。
- 氏名、生年月日などが記載されていることを確認する
- 基礎年金番号について申込時に入力済みなら反映されている内容を確認(当時、入力していなければ記載が必要)
- 配分が指定した内容に沿って反映されているか確認(訂正が必要な場合、記載例に沿って修正が必要)注
- 記入日を記載
注:配分を訂正する場合、合計が100%になるよう注意する(もしくは加入完了後に、開設された口座内でオンライン手続きを行う)
配分指定はオンライン申請時に入力済みですので、変更なければさらっと確認。
わたしの場合、基礎年金番号はすでに入力済み、配分割合も変更なしです。
そのため、記入日のみを記載して完了しました。
加入者等運営管理機関変更届 (資料④とした書類)
こちらの書類は「移管元から移管先への手続きを進める情報」を提出するために必要な書類です。
具体的には以下のような内容を含んでいます。
- 移管元と移管先に関する登録番号、名称といった情報
- 移管元からの移管先の各商品へどのような割合で移管するかを指定する情報
こちらも以下の部分に注意して確認・記載しました。
- 基礎年金番号(記載なければ記入が必要)
- 氏名(自筆で記入が必要)
- 生年月日(入力内容を確認)
- 住所・電話番号(入力内容を確認)
- 変更前の”運用関連 運営管理機関”の「登録番号」と「名称」(下の参考欄参照)
- 変更前の”記録関連 運営管理機関”の「登録番号」と「名称」(下の参考欄参照)
- 移換時配分指定書(個人型)欄がオンライン申請時の配分割合となっているか確認、必要に応じて記載例をみながら訂正 注
- 記入日を記載
- すべて記入後、最終ページを「本人控」として切り離す(移管完了までは大切に保管しておく)
注:配分を訂正する場合、合計が100%になるよう注意する(訂正は記載例に従う)
少し手間なのは、変更前の「運営管理機関」の2箇所ではないかと考えます。
- 運用関連 運営管理機関・・・楽天やマネックス証券などの窓口となる会社
- 記録関連 運営管理機関・・・楽天やマネックスが記録管理を任せている会社
といった違いです。
運営管理機関登録事業者の一覧はこちらで調べることが可能(外部のPDFへリンク)
(わたしの例)
- 変更前の運営管理機関:楽天証券⇒上のリンクから登録番号774を確認し、7桁を埋めるよう「0000774」と、名称を記載
- 変更前の記録関連期間:JIS&T(日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー(株))⇒同リンク先から登録番号11を確認、7桁のため「0000011」と、名称を記載
どの証券会社がどの記録関連運営管理機関を利用しているかは、「○○証券 iDeCo 記録関連運営管理機関」など、自身で検索して調べてみる必要はあります。
ちなみに、マネックス証券と楽天証券は同じ記録関連運営管理機関を利用されています。
この場合であれば、上記のように「日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー(株)」の登録番号と名称を記載すれば問題ありません。
ちなみに、SBI証券の場合「SBIベネフィット・システムズ株式会社」だったりします。
一概に一緒とは限らないので、注意が必要でしょうが、調べてみればすぐに分かるとは思います。
そこまで手間ではないでしょうから、この部分が面倒で躊躇する必要はないと考えます。
これらの書類を同封し、返信用封筒で返送すれば対応は完了!
自身で対応が必要なのはここまで。
返信後は、移管元(わたしの場合、楽天証券)と移管先(同、マネックス証券)間などで随時、移管手続きが進みます。
今後のイメージは、以前の記事でも書いていますが、
- 移管先で関係箇所と移管手続き開始(国民年金基金連合会での審査もあり)
- 移管元と連携し移管準備が進む(準備として定期預金以外の資産売却あり)
- 移管先口座開設のお知らせとパスワードがJIS&T(※)から届く(まだ取引はできない)
- 移管先、移管元で資産移管準備が続く
- 移管元から残高証明書が届く
- 記録管理機関のJIS&Tから「移管完了通知書」が届く(これで資産購入が可能)
といった流れで進みます。
ということで、資料到着〜返信までの流れをまとめておきました。
あとは気長に移管完了を待ちます。
手続き自体は非常に簡単です。
別に移管をオススメするわけではありませんが、対応を検討されている方の参考になれば嬉しいです。
しばらく更新をサボっていましたが、2023年8月に記事投稿を再開し、移管の実績を簡単にまとめておきました。
↓移管実績の紹介はこちら↓