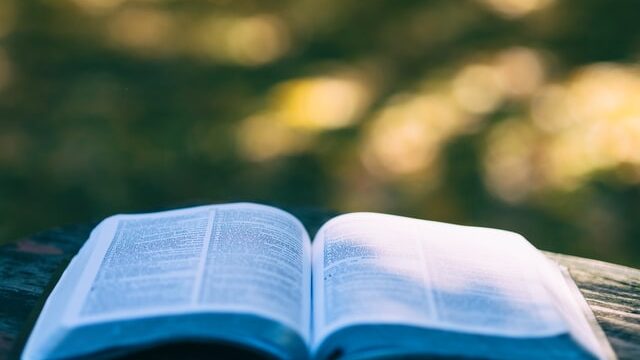こんにちは、おーです!
本日は「LIFE SHIFT2―100年時代の行動戦略」という本の感想をご紹介させていただきます。
【感想】LIFE SHIFT2―100年時代の行動戦略
常に学び続ける、行動し続ける

2020年に始まったコロナウィルスの蔓延といった今までの常識、世界観を覆すような出来事が起こっていること、テクノロジーの進歩などによる長寿化がますます進んでいくことなどから、わたし達の生活環境は、過去と大きく考え方を変える時期に来ているとも言えます。
- 健康
- 資金
- スキル
- 生き甲斐
- 人間関係 など
今までより寿命が長くなる可能性が高い時代が訪れているということは、これらのことに、今まで以上にもっとフォーカスしていく必要があるとも言えます。
- より長く少しでも健康的に
- より長く資金の心配をしなくてもいいように
- より長く働いたり、健康でアクティブに生産的な活動をするためのスキルや生き甲斐を見つけ、磨き
- より良い人間関係を築く
といったことが、これからさらに自身の責任のもとに問い続けていく必要がある世界が到来していることを実感できます。
本書では架空の世代、国を超えた登場人物を用いて、上記のような問いに具体的な問題点を投げかけ、行動戦略を紹介しています。
昔では一部の人にしか考えられなかった「長寿」、さぞ喜ばしいことだったのでしょう。
逆に現代では世界がかかえる難問になりつつある課題とも言えることが認識できます。
- 健康的でなければより楽しめない(かもしれない)
- 資金に余裕がなければより苦労が多い(かもしれない)
- やりがいなどがないと長寿が苦痛になる(かもしれない)
- 人間関係が希薄だと楽しみ、幸福感、満足感も減ってしまう(かもしれない)
価値観は人それぞれですので、これは推定でしかありません。
ですが、本書で言われるような現代の恵まれた時代における『長寿の配当』を得るには、上記のようなことを意識して、自分や家族の(長寿化を見据えた)生活設計、マインドセットの大切さを改めて求められているように考えます。
変化の激しい現代において少しでも恩恵も受けられるよう、「常に学ぶ姿勢、行動する姿勢」を忘れずに生活していきたいと、考えを新たにすることもできました。
世代・年齢に対する見方、認識を変える
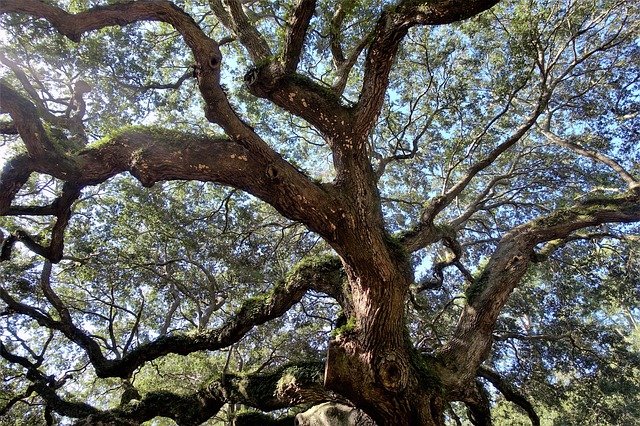
かつて60歳を超えると「定年」といった年齢一律の捉え方などがありましたが、すでに過去の遺物となりつつあります。
若々しい60代、70代の方なども多い現代において、かつての年齢に対する捉え方、社会規範では長寿化という課題に対するハードルを上げているとも言えそうです。
まだ働きたいのに(バリバリ働けるのに)、例えば50代、60代になったから自動的に給料体系が見直される、などといった画一的な対応ではなく、もっと柔軟にこのような人生経験豊富な世代の、若者がもっていないスキル、経験といった財産を有効に、少しでも長く社会で活躍してもらうことが喫緊の課題として企業にも求められていると感じます。
少子高齢化が進む日本において、このような「暦年齢」によって画一的な線引をすることは、もはや現実的ではないでしょう。
このような問題点に対し政府も動いているところですが、肝心の企業は考え方がすぐに変わるのでしょうか。
本書では「暦年齢」で考える画一的な捉え方の限界や問題点を、「年齢のインフレ」や「年齢の可変性」といった興味深い考え方をもとに、疑問を投げかけています。
国全体をあげて過去とは違う年齢に対する意識を浸透させていく必要があるということが、本書を読むことで改めて認識できました。
長寿化を見据えた俯瞰した捉え方をする

生活しているいま現在、どうしてもこの点にフォーカスしがちになります。
視点で言えば「近くのものが大きく見え、遠くのものが小さく見える」といった感覚です。
将来わたし達がより長く人生を謳歌することができるかもしれない、長寿化を恩恵という形で得るためには、近視眼的な見方から視点を変える必要があるともいえます。
「今も大事だけど、将来を考えることも大事」という、全体を俯瞰してみようという捉え方も求められる時代が到来しているということです。
もう少し寿命の短かった過去であれば引退→年金生活で余生を十分に過ごせたのかもしれませんが、今後は(今よりさらに)テクノロジーや医療も加速的に進歩する可能性もあります。
人間の行動心理的に、目先の損得や直近の出来事ばかりにフォーカスしがちですが、長寿化により様々な点において恩恵を受けるためには、現在を大切に思うことと同じくらい、将来を大切に考えることも問われています。
わたし達の一挙手一投足が、現在のみならず未来にも繋がっている、このような意識を強く持つ必要があるということを改めて認識しました。
政府発表の平均寿命より長く生きる可能性に対する認識

本書では、政府が平均寿命として公表しているデータは、平均寿命の”延び”を過小評価している可能性を指摘しています。
平均寿命の算出には「コーホート平均寿命」と「ピリオド平均寿命」と呼ばれる、2種類の方法があるようです。
- ピリオド平均寿命:○○年に生まれた子供が○○年の医療水準(この水準が今後もキープされると仮定された)で生涯を生きると仮定
- 2019年に生まれた子供が2019年の医療水準のもと、65歳(2084年)になったとき死なずに66歳まで生きる確率=2019年の65歳が2019年に死亡しない確率と同じ
これに対してコーホート平均寿命は、
- コーホート平均寿命:時代を経ていくにつれ、死亡率が低下することを前提に計算
- 2084年の65歳が同じように66歳まで生きる確率は、2019年の65歳が66歳になる確率より高いと評価
このような違いがあるようです。
実際、算出してみた結果(一部の例として)、コーホート平均寿命のほうがピリオド平均寿命より約10年、平均寿命が延びるといった結果が本書では紹介されています。
コーホート平均寿命のほうが医療の進歩などを加味して、より現実的な値が示される印象ですが、このような点を考えると、テクノロジーや医療の進歩を反映して長寿化はさらに長い人生をもたらすことになるかもしれません。
このような点からも、現在と同じくらい将来に備える意識をより強くする必要があると捉えることもできるのではないでしょうか。
本書はわたし達の、まだまだ先の長い将来に対する認識を改めて、気づきを与えてくれる非常に勉強になる一冊でした。
その他にも世代を超えた交流の必要性などといった実際の生活に必要で、役立ちそうな考察もあり、少なくとも将来に対する備え方、考え方や視点が広がるように思います。
簡単ですが感想のご紹介とさせていただきます。
この記事がなにかの参考になれば幸いです。
それではまたっ!!