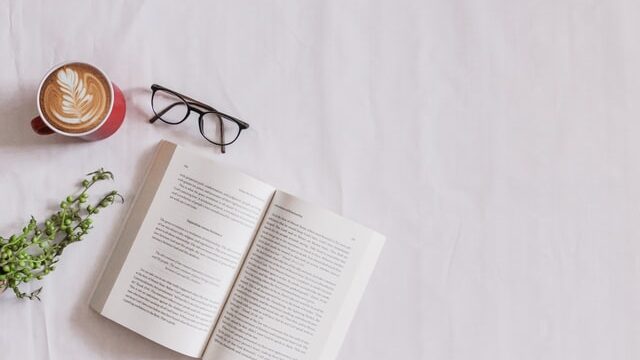こんにちは、おーです!
本日は「世界のエリートがやっている最高の休息法」という本読んで感じたことをご紹介させていただきます。
【感想】世界のエリートがやっている最高の休息法
書籍の紹介
著者は日本と米国で医師免許を持ち(かつ医学博士)、世界有数の有名大学「イェール大学」で先端脳科学研究などにも携わった後、アメリカでメンタルクリニックを開業され、最先端の治療法などを取り入れつつ診療をされている、久賀谷 亮(くがや あきら)氏が書かれた書籍です。
経歴からして優秀であることは一目瞭然です。
本書は氏が最先端の脳科学研究などに携わった経験と、その経験からも、より注目度が高まっているマインドフルネスの有効性、その有効性を世界の超優秀な一流エリートが認め実践していることなども交えつつ、紹介されている本です。
本書はストーリー形式で進行する物語がメインで、主人公や関係者の苦悩などに対し、対応できるマインドフルネスの効果的な実践手法や、その手法などに対する脳科学の観点からの有効性、脳のみならず全身に与える効果などを学ぶことができます。
マインドフルネスという(ある意味掴みどころのない)ものを、できるだけ平易にわかりやすく紹介されています。
脳の疲労と肉体の疲労を区別し、脳の休息にアプローチを考える

よく、体を休めたり、休息をとるときには「睡眠を取ろう」、「何もせず体をしっかり休めてリフレッシュしよう」、「避暑地などで心身をリフレッシュさせよう」など、頭に浮かぶと思います。
そして休息をとってはみるものの・・・
結局、「休んだのになんだか疲れがとれていない気がする」と感じることもあるのではないでしょうか。
わたしもそのようなことはよく実感するところですし、歳なのか・・・とも考えたりしてしまいます。
このようなリラックス方法はある意味で効果もあるでしょうし、大切なリフレッシュの一種であることは確かだと思いますが、本書では「脳には脳の休め方がある」というアプローチから紹介が始まります。
- パフォーマンスを高めるため
- 様々な観点からリフレッシュなどをより有効なものにするため
本来、肉体を休めることと、脳を休めることは根本的に対応方法が異なるという前提の対応が必要ということです。
疲労の慢性化が人生の様々な質を下げかねない、そして精神的な疲労にも繋がる、命題に対し、最新の脳科学的な観点から、脳の疲労回復などに効果が期待できるマインドフルネスの有効性に、より注目が集まっています。
一流エリートがなぜマインドフルネスを実践しているのか
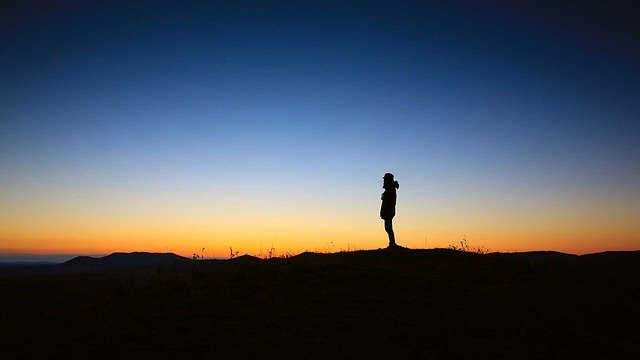
本書では以下のような一流エリートや一流企業などのマインドフルネス実践・導入を例として紹介されています。
- アップル創業者 故ステーブ・ジョブズ
- ツイッターなどの創業者エヴァン・ウィリアムズ などなど
- 企業でもグーグルのサーチ・インサイド・ユアセルフという取り組みは有名
- パタゴニア(アウトドアブランド)でも研修の導入が進む など
実利を重視したり、本当に役立つものしか手を出さない、現代ビジネスの最先端を突き進むような一流エリートや、世界的に有名な一流企業。
自由の国アメリカでとくに成果の求められるような(立ち止まれないような)環境でも成果を出し続けるこのような超一流エリートなど。
このような人たちを含め、なぜマインドフルネスという(ある意味で得体のしれないようなもの)を実践するのか。
理由は「脳の休息と、そのためのメソッド」がとにかく大切であることを知っていて、それを実践している(そのために有効な手法がマインドフルネスに他ならない)ということでした。
体の疲れは、ある意味、寝れば回復したりもしますが、脳は四六時中、活動しています。
たとえば休日にリラックスしているように感じていても(わたしたちが意識していなくても)、脳はある種の活動をしています。
脳が意識的に活動していないときでも、実はその時の脳活動は「脳の消費エネルギーの60%〜80%を占める」非常に大量のエネルギーを消費しているようです。
『脳は体重の2%ほどしかない』と言われるようですが、脳の消費エネルギーは全身が消費するエネルギーの20%も使う、大量消費の部位ということでした。
そしてそのうち、アイドリング状態(脳が意識的に活動していないとき)でも、エネルギーの60%〜80%が使われている、といえばかなりの割合を占有する大量の消費量です。
アイドリング状態の『雑念など』にこのような大量のエネルギーを消費してしまっていては脳が休まらないのは当然かも知れません。
忙しく、マルチタスクをこなすことを求められがちな現代です。
休んでいるときでも頭の中は常に何かを考える時間が続いていますので、真に休めてはいないともいえそうです。
いま以上に「脳単体と脳を通じた全身の疲労回復」に注目した取り組みの必要性が高まっている時代はないかもしれません。
活動中はフルに活動してエネルギーを大量に消費している脳、そしてアイドリングしているだけなのにエネルギーが大量消費されてしまう脳。
この脳を『意識的に休ませる』こと。
疲労感を感じにくくする脳を作っていくためには「脳の休息法」を学ぶ必要があるということがわかります。
マインドフルネスで「意識的に脳を休ませる」ことができれば、疲れづらい脳が手に入り、疲労感のさらなる回復と、より高まることが期待できる集中力などで、日常のパフォーマンス向上にも繋がることにも期待ができます。
疲れない脳を自分の取り組み次第で作れる

マインドフルネスを実践し続けることで「脳を一時的に」ではなく、「構造そのもの」を変えることも可能なようです。
これは脳には「可塑性」といわれる、訓練を続けることで脳を変えることができる性質が備わっていることが要因です。
雑念などで大量消費されるエネルギー。
脳を休ませることで意識的に活動をコントロールすることができれば、疲れにくい脳が手に入り、人生の質をより高められることにも繋がりそうです。
その他にも以下のようなことに効果が期待できるという研究結果もあるようです。
- 集中力の向上
- 感情調整力の向上
- 自己認識に対する変化
- 免疫機能の改善
要は総じて、自身の心身健全に対し、マインドフルネスはもってこいの取り組みと言えるのではないかと思います。
半信半疑でも「まずはやってみる」という行動力が、やらなくて何も変わらない・気づけないというケースよりも、何かを変えるきっかけになるのは必然です。
様々な手法が豊富に紹介されている

本書ではまず、ストーリーに入る前に、前段として脳を休めるマインドフルネスの手法が紹介されています。
これは本編のストーリーでも登場する手法で、ストーリーを読んでから改めて読み返すことで、よりイメージなどがつきやすくなっています。
(それぞれの手法が紹介されているストーリーともリンクしています)
マインドフルネスの手法が色々あるというと、知らない方は難しく感じるかもしれませんが、手法自体はすべて簡単なものです。
アプローチしたい内容によって、いろいろなイメージの広げ方があるんだな、ということが整理できるような内容と、簡単なイラストもついています。
本書を読めば、マインドフルネスというものに対するイメージを広げることができ、そして実践してみることもできます。
最後はやるか、やらないか、ただそれだけ(その差は大きいかも)

はっきり言って、マインドフルネス自体に取り組むことにお金は必要ありません。
- 場所
- 時間
- 取り組む意識
これらがあれば、いつでもどこでも取り組めます。
少しだけの本(もしくは無料の動画)などで1人でも簡単に知識を仕入れることができます。
あとは自分なりに実践を続けるだけです。
- 仕事の休憩時間でも意識を呼吸に向ける
- 歩いているときに意識を歩行に集中させる
- 歯磨きのときに意識を歯磨きの動作に集中させる などなど
何をしているときにでも、マインドフルネスの取り組みとして体験してみることはできます。
お金のかからない取り組みで、かつ脳を休ませることができ、また集中力なども高められ、最終的に疲労回復にも効果的。
これ以上の手軽さを兼ね備えた手法はなかなかないのでは。
わたしも本書を読む前から、かれこれ1年以上、毎日10分程度、取り組んでみてはいます。
はっきり言って、雑念が浮かぶことなど日常的です。
意識が集中できず、時間が終わることなどしょっちゅうです。
そうかと思えば、集中できて頭がスッキリする、となんとなく効果を感じることもあります。
そして逆に、そのような感覚を感じないことはより多くあります。
毎日、同じシチュエーションで過ごすことなどありませんから、昨日と今日の雑念は違ったり、明日はまた違うことが浮かぶのでしょう、そんな繰り返しです。
それでもめげずに、淡々と、意識を自分の中に傾けて続けてみる。
雑念が浮かばないことが目標ではなく、雑念と距離をおける心持ちに少しでも近づけないか。
雑念と距離をおくことで、日々、過剰に動き混乱する脳を一時的にでも休ませられることに繋がれば、効果としては十分かもしれません。
よく言われるのは、過去でも将来でもなく『いま』に集中する。
言葉にすれば簡単ですが、実際には雑念などに占有され、非常に難しいことです。
瞑想は自分と向き合う時間を確保するための最も簡単で、手軽で、いつでも、お金がかからずにできる、言うことなしの取り組みだというのが個人的な感想と、これからも続けていきたい理由です。
失敗したと思ってやめたとしても、失うのは時間くらいなものです(時間は貴重ですが、この取組はさらに貴重だという個人的な認識です)。
仮にやめたとしても、実践してみた取り組みは経験として残ります。
時間が経ってまた改めて取り組んでみようという意識にも繋がるかもしれません。
日本ではまだ声高に言われることはないのかもしれませんが、実利を重視するアメリカではマインドフルネスはすでに流行しているようですね。
万人にあうかはわかりませんが、マインドフルネスで得られる気づきなどがもし、広範に広がれば、個人だけではなく、人と人同士の関係性すら改善できるかもしれません。
個人の活動にとらわれない、色々な可能性すら秘めていそうです。
何を聞いても、最後の行動は自分次第です。
わたしは本書を読むことで、これからも引き続きマインドフルネスへの取り組みを続けていきたいと思えましたし、思いを新たにすることもできました。
思い立ったら物は試し、はじめてみるのもいかがでしょうか。
それではまたっ!!