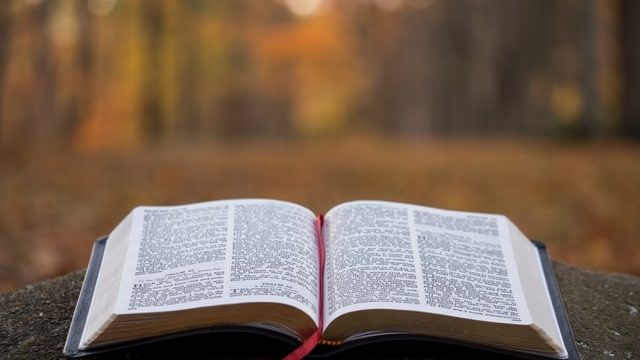こんにちは、おーです!
本日は「2040年の未来予測」という本読んで感じたことをご紹介させていただきます。
【感想】2040年の未来予測
書籍の紹介
著者は元日本マイクロソフトの社長を務められた成毛眞氏です。
経歴からもテクノロジーに精通されていることは一目瞭然です。
本書は、誰にでも(生きている以上、避けることのできない年齢の経過とともに)訪れる将来の変革として、テクノロジーのもたらす明るい側面と、日本に待ち受ける暗い(個人が考えなければいけない)側面などを、日本人著者の視点で、日本の将来を俯瞰して考察された内容となっています。
テクノロジーの進化がもたらす「予想される将来の姿」といった話以外にも、日本で生活するうえでの将来を見据えた「行動の変革」などについて、知っておいたほうがいい有用な内容です。
テクノロジーの進化を怖がらない
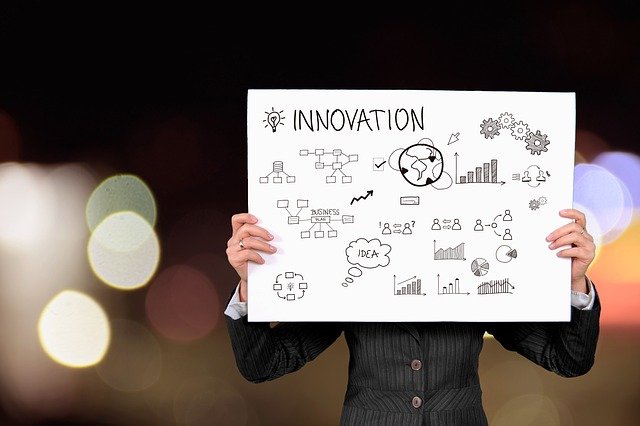
スマートフォン(iPhoneなど)の登場、普及以降、わたしたちの生活水準が飛躍的に高まったかと言われるとそうではないのに、ここ10年程度で「生活の質や行動など」は大きく変わってしまいました。
テレビで「テレビ局が制作した情報」を受動的にみる時代ではもはやなくなりました。
スマホでゲームや友人たちとの交流、ショッピングなどの自分がしたいことが簡単にできます。
スマホで興味のあること、知りたいことなどを簡単に、テキストや動画という様々な形で調べたりすることができます。
自分たちが欲しい・必要な情報に対し「能動的に行動し、意識的にアプローチできる」時代が訪れています。
わたしも含め、はじめは懐疑的な人も多かったかもしれませんが、たった10年程度で(スマホという小さな、でも大きな存在のアイテムだけを見ても)生活スタイルを揺さぶる変革がもたらされました。
情報技術の進展は、今までに発展してきた様々なものたち(点同士)が、さらに融合し、新しいものが(点と点が線や面となって)広がることが予想されます。
残念ながら減少することがほぼ間違いなく確定しているわたしたち日本の将来の人口です。
このような流れに対し、生産性や生活の質などを維持するためにも、テクノロジーへの依存が今後より高まることが想像されます。
そのような環境において、アナログすぎる考え方は、時代についていけなくなる可能性が高まりそうです。
目新しいものは小難しくもあり、とかく敬遠しがちになる分野かもしれません。
ですが、これから開発されるであろう様々な技術は、わたしたちの生活環境、職場環境に大きな影響を与えることは必死です。
過去、テクノロジーが進歩してきたスピードとは異なり、これからは様々なテクノロジーが融合し、進化の速度は増していくことは容易に想像できます。
通信環境が5G(もしくはさらに先の6G)になると、大容量のデータが転送・活用できることで、今まで以上にテクノロジーの進化、恩恵を受けられる世界が訪れることが本書では紹介されています。
家の中をみても様々なものがインターネットにつながることで利便性は更に向上するでしょう。
それに伴って(モノが繋がっていなかったときと比べれば)、リスクも大きくはなる懸念はありますが負の側面にこだわるのか、便利になる明るい方向に視点を向けるのか、考え方はそれぞれです。
VR(バーチャル)やAR(拡張現実)などの可能性が飛躍的に高まることも予測されています。
そのような環境をどのように捉えるのか。
歳を取ると新しい知識を吸収することを面倒に感じることもあるかもしれませんし、柔軟な考え方がしにくくなる、懸念もあります。
知らないから触らない、見ない、聞かない、といった凝り固まった考えに取り憑かれていると、世間と隔絶して殻にこもるしかなくなるかもしれません。
100%安全で安心できるものなど理想でしかないでしょうし、すべての情報を仕入れ、すべての安全を確認してから行動することはできません。
例えば興味のある部分からでも、新しいものに触れてみるというのは、新たな刺激を取り入れながら、技術革新の恩恵を享受するためには必要な考え方ではないかと思います。
選択肢を広げられるのは「いま」考え、備え、行動をはじめている人

将来に向けて、以下のような選択肢が取れるとします。
- 自分なりに将来へ向けて情報を仕入れて種を蒔く
- 現時点で問題はないからと漫然と今を過ごし考えることを後回しにする
いずれも現在において差は目に見えないほど小さいかもしれません。
ですが、激変するであろう将来の社会構造、確実に訪れる「いま」とは異なる自身の老い(働けなくなるかもしれない懸念)などに向けて、備えられるのはどちらの人でしょうか。
- 人口減少が確実視されている日本
- 減りそうだと考察されている年金
- 確実に来る将来の老い
- 働けなくなる可能性
これだけでも十分に不安ですが、さらに不確実な要素を上げれてモヤモヤと考えればキリなどありません。
例えば、長くなりそうだと思われる労働期間に対し、リタイアできる選択肢を持てる人はどのような人でしょうか。
楽しいから働くという人はいいでしょうが、お金が少ないから渋々働くという人も少なくないでしょう。
「長く働いてもいいし、働くことをやめても将来に向けて備えていたお金を頼りにリタイアもできる」というのは、コツコツと備えを積み上げている人が持てる贅沢な選択肢になるのかもしれません。
日本の環境で確実に言えることは、将来に備えるためには、過去のお金に対する(わたしたちが親から教育を受けてきたような)古い考え方を改める時代に来ているということです。
- (国の公的制度を理解せず)親から勧められたり、安心できるからと漫然と保険に入り、毎月過剰に無駄な保険料を支払い続ける
- (安全だからという理由だけで)投資などを学ばず金利のつかない銀行に預貯金でお金を寝かせておく
例えば2022年現在、日本でも物価の上昇が見受けられ始め、ニュースで報道されることが飛躍的に増えました。
このようなインフレ環境下で預貯金でお金を寝かせておくということは「増えない投資先に預けて、お金に働いてもらう必要はないという判断と選択」をしているとも捉えられます。
(預貯金という形でお金を預けておくという行為も投資ですので、この点を十分に把握しておく必要があります)
このような環境が長く続けばどうでしょうか?
物価が上昇している(上昇していく)なか、相対的にお金の価値は減少していくことになります。
わたしたちの親世代(高金利な時代があった頃)は銀行預金が魅力的な時代もあったようです。
でも現在ではほぼ金利のつくことがない身近な銀行に「とりあえず安心できそうだから」と預けてお金に働いてもらわない選択をするのは、もはや「自分でお金の価値を減らしている」とも捉えられます。
(普遍的な金融教育を受けている方は別ですが)親世代とは時代背景も、環境も異なる現在、もはや親世代から学んだことが通用する時代ではないとも言えるかもしれません。
預貯金と安心、安全が大好きな日本人は、よく「お金好き」とも揶揄されます。
でも考えてみればそのような方たちが、お金の価値が下がる場所にわざわざお金を預けておくというのは、なんとも不思議な話ではないでしょうか。
インフレはあくまでただの例ですが、これからの日本では各家庭でお金などの知識を増やし、将来に備えていく必要があることも学ぶことができます。
知ろうとして学び、そして学びを行動に繋げられる人だけが、将来の選択肢を少しでも多くもてることに繋がりそうです。
日本の将来を俯瞰して考えるのに、本書は非常に読みやすく、わかりやすい表現で記載されています。
ボリュームもそこまで多くないので、短い時間で読むことができると思います。
自分たちなりの持ち得るどんなピースを組み合わせ将来に備えるかは各家庭、個人の自由です。
そしてピースは学ぶことで増やす事ができ、様々な組み合わせ方に発展できると思います。
週末などの時間を有効に活用し、このような未来予測を踏まえつつ、自分たちの将来を俯瞰して少しでも考え、行動で選択肢を広げてみるのもいかがでしょうか。
それではまたっ!!